【認知症(痴呆)とはどんな病気か?】
成人におこる認知障害でその症状は進行性です。記憶が低下し、新しいことを覚えられず、以前の事を思い出すことが困難になります。
認知障害には、言葉のやり取りが出来ない(失語)、適当な認識ができない(失認)、道具を使うことが出来なくなる(失行)、計画を立てたり手順をふむ作業が困難となります。(実行機能の障害。)
このように、記憶、判断、言語、感情など、いろいろな精神機能が減退し、さらには消失するため、日常生活に支障をきたします。
【「痴呆」から「認知症」への名称変更】

痴呆という言葉には軽蔑的な意味が含まれ、「痴呆」の高齢者に対する軽蔑や労わりを欠く表現です。また、一旦、痴呆になると、元に戻らないとの考えが強く、家族や地域に理解されない現状があります。本人及び家族などが長寿を慶び、自分らしく生きることができるよう関連団体や一般からの意見を募集し、厚生労働省では、高齢者介護を更に積極的に進めるためにも、「認知症」という新しい名称を用いることにしました。(平成16年12月)。
【認知症の原因は?】
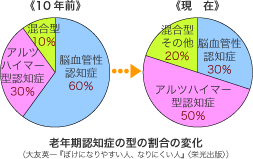
原因となる病気はアルツハイマー型認知症と脳血管性後遺症です。
この2つの病気で認知症全体の80~90%になります。
アルツハイマー型認知症はβ-アミロイド蛋白といわれる異常な蛋白質が脳に広く蓄積し、そのため神経細胞が変性し脱落する病気です。なぜこの異常蛋白ができるのかは、まだ十分には分かっていません。
極めて稀な、特殊な型に家族性発症というのがあります。この型には、いくつかの遺伝子が原因となると報告されています。
脳血管性認知症の原因としては、脳出血、脳梗塞などの後遺症があります。有効な薬の開発により血圧のコントロールがうまく行われるようになり、脳出血は少なくなりました。しかし、脳梗塞の小さな発作が多発し、脳の白質が広範に侵されると、認知症を来たすことになります。
以前は、この脳血管性の認知症が多かったのですが、最近では、アルツハイマー型のものが多くなってきています。
このほかに、前頭側頭型認知症(大脳前頭葉や側頭葉前部が萎縮し、性格変化と社交性の障害が初期より認められる。65歳以下の発症が多い。ピック病がその代表例)、レビー小体病(進行性の機能低下と幻視、パーキンソニズムを認める。病初期にはアルツハイマー型認知症との鑑別が困難なことがある)、パーキンソン病、慢性硬膜下血腫、正常圧水頭症、脳腫瘍、脳炎、クロイツフェルト・ヤコブ病、エイズ脳症、アルコール脳症、甲状腺機能低下症などでも認知症の症状が起こる可能性があります(原因となる疾患を治療すると認知機能が改善する可能性があるので、治療可能な認知症といえる)。
【認知症と物忘れ(健忘)の違いは?】
ある程度年を取ると人の名前や物の名前がとっさに思い浮かばないことを経験するようになります(度忘れ)。しかし、大抵その日の内に思い出すことができます。一方、認知症では、今朝、食事をしたことすら思い出せません。物忘れでは朝食を食べたことは覚えていますが、献立までは思い出せないといった状態です。このような物忘れは年齢相応の生理的現象と考えられていました。しかし、最近の研究では、日常生活には障害はないのですが、年齢相応以上に物忘れのひどい人では、約8%が5年後に認知症となることが報告されています(軽度認知障害)。早期発見、早期治療が大切です。
【認知症の症状は?】
認知症の症状は大きく2つに分けることができます。
- ■中核症状:
- 認知症の中心となる症状です。認知機能の障害(記憶障害、失語、失行、失認)のため、時(年月日、曜日、季節など)、場所(自宅、職場など)人(家族や知人の顔など)が分からなくなります。また、思考力や判断力が低下します。
- ■周辺症状:
- 知的能力が低下するため、二次的に起きるものです。行動と精神症状です。人によって扱われる場合とそうでない場合があります。
行動の異常としては、落ち着きのなさ、暴言、暴力、脱抑制、過食、拒食、異食、攻撃性、徘徊、常同行動、不適切な行動、無言・無動などです。
精神的な異常は、うつ状態、不安、緊張、いらいら、興奮、易刺激性、妄想(物を盗まれたと主張する)。幻覚、多幸、意欲低下、無為、無関心などです。
中核症状(認知機能の障害)のため、周辺症状が二次的に生じるという考え方に対し、BPSD(認知症に伴う行動障害と精神症状=周辺症状)という提案があります。認知障害の程度とはとくに関係なく、認知症の中期に問題行動などが出現(患者の約6割)し、介護者に大きな負担となりますが、適切な対応で軽快します。
【認知症の診断は?】
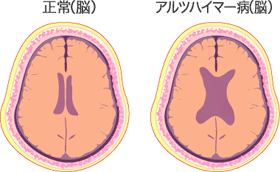
身体的な疾患が原因となることがあります。そのため、身体的検査(尿、血液検査、内分泌検査、胸部X線、心電図など)を受けます。
脳の一般検査としては心理学的診断のほか、脳波検査、脳背髄液検査と脳画像診断検査、(CT、MRI、SPECTなど)です。
また、知的機能のための心理テスト(長谷川式簡易知能評価尺度など、また、柄澤式テストでは本人を良く知っている人から聞くことで検査ができます)も行います。
診断はこのようないくつもの検査の結果を総合的に評価して決定します。
認知症の原因となっている疾患が特定できますと、その治療により改善が期待できます。
【軽度認知障害とは?】(Mild cognitive impairment, MCI)
MCIは認知症と知的には正常ともいえない中間の状態であり、早期発見、早期治療のため慎重に対応しなければなりません。
- 物忘れの訴え
- 長谷川式簡易知能評価尺度でおよそ20~25点(30点満点)位
- 日常生活に支障はない。
などと定義されています。
MCIとされた人がすべて認知症へ進行することはない。90歳以上の認知症では、正常老化による記憶力低下やMCIとの境界が曖昧となる場合がある。
複雑な仕事の遂行の困難や判断力の障害も考慮して軽症や発病前の人に対する予防的対応にも積極的に当たるべきでしょう。
【認知症の薬物療法とは?】
認知症治療の原則
認知症高齢者は環境やケアの影響を大きく受けます。
ケアでは、まず、なじみの人間関係を大切にし、高齢者特有の心や言動を受容・理解し、その心身の動きやペースに合わせてよい交流を図るようにしましょう。理屈による説得は反発されることが多いので、納得してもらうことが大切です。高齢者を孤独にさせないようにし、安易に寝たきりにしないことなどに注意し、廃用低下を進行しないようにします。高齢者は環境の変化に適応が困難です。彼らには過去も未来もありません。「今」の安住をはかるように努めましょう。周辺症状(BPSD)が高度で患者自身や周囲の安全が守られない場合、薬物療法の導入となります。
高齢者は心肺機能、肝胃腸機能など低下していますので、処方は正常成人量の1/2~1/4量から開始し、増量には間隔を長くします。身体合併症がある場合、可能な限り多剤投与は避けるようにします。服薬回数は少なくすると服薬コンプライアンスが向上します。
抗認知症薬による治療
認知機能障害に有効な薬物は、コリンエステラーゼ阻害薬のドネペシル(アリセプト)、ガランタミン(レミュール)、リバスチグミン(イクセロン、リバスタッチ)とNMDA、受容体桔抗薬のメマンチン(メマリー)の4種類でます。コリンエステラーゼ阻害薬はいずれも中核症状の進展を抑制する効果が期待されます。認知症の諸症状が劇的に改善しないとして、そのため服薬を中止すると症状が急激に進行・悪化することがあるので、このことについて患者や家族へよく説明をしておくことが必要です。
- (1)ドネペジル
- 軽度から高度のアルツハイマー型認知症が適応です。
意欲、言動など日常生活上の改善が期待できます。ドネペジルで易怒性が出現した場合は、メマンチンの併用が有効です。本薬少量がレビー小体型認知症に有効なことがあります。 - (2)ガランタミン
- 軽度から中等度のアルツハイマー型認知症に用います。
臨床効果はドネペジルと同様です。レビー小体型認知症で有効なことがあります。 - (3)リバスチグミン
- パッチ剤です。拒薬する患者や飲み忘れの見られる患者には使いやすいでしょう。軽度から中等度のアルツハイマー型認知症が適応です。背部、上腕部、胸部の正常で健康な皮膚に貼布をして、24時間毎に貼り替えます。
レビー小体型認知症にも効果があります。 - (4)メマンチン
- 中等度から高度のアルツハイマー型認知症が適応です。本薬は、感情の安定化が期待できます。
| 種類 | 一般名 | 適応となる 認知症の程度 | 用量 (㎎/日) |
用法 (回/日) |
注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| AChE阻害薬 | ドネペジル | 軽度~高度 | 3-10 | 1 | 興奮系薬剤 |
| ガランタミン | 軽度~中等度 | 8-24 | 2 | 弱興奮系薬剤 消化器系副作用 |
|
| イクセリンパッチ リバスタンパッチ |
軽度~中等度 | 45-18 (パッチ剤) |
1 | 弱興奮系薬剤 消化器系副作用 皮膚症状 |
|
| NMDA 受容体拮抗薬 |
メマンチン | 中等度~高度 | 5-20 | 1 | 鎮静系薬剤 BPSD緩和にも期待 副作用として過鎮静 |
治療薬の選択
軽度の患者では(1)、(2)、(3)のいずれか1剤を選択し授与し効果がないか、不充分な場合には、他剤への変更を試みます。中等度の患者で治療を開始する場合は(1)、(2)、(3)、(4)のいずれかを選択します。効果がないか、不充分な時は他剤へ変更します。(1)(2)(3)のうちの1剤と(4)の併用または追加を考慮します。
重度の場合は、ドネペジルの増量(10mg/日)やメマンチンの追加をします。
効果なし、もしくは副作用出現の場合は、慎重に検討の上、投与を中止します。
周辺症状(BPSL)の治療
原則として投薬は少量から開始し、可能な限り短期間の投与とし、有効性や有害事象出現など検討します。
- 夜間せん妄
- 原因をチェックし対応する(感染症、熱発、脱水、薬物など)。リスペリドン、オランザピン、アリピプラゾール、チアプリト、などを用います。
- 不安
- 軽度の患者の不安に対しては、短期間ないし中期間作用型のベンゾジアゼピン系薬物(エチゾラム、クロチアゾパム、ロラゼパム、アルグラゾパムなど)が用いられます。中等度から高度の患者では、過鎮静、運動失調、失見当識など有害事象が出現し、記憶障害が増悪することがあります。そのため抗精神病薬のリスペリドンの使用量の方が安全で有効です。
- 焦燥性興奮
- 非定型抗精神病薬(リスペリドン(リスパダール)、クエチアピン、オランザピン、アリピプラゾール)が有効です。メマンチン、抑肝散の有効例があります。
- 幻覚・妄想
- リスペリドン、オランザピン、アリピプラゾールの使用が推奨されています。非定型抗精神病薬は適応外使用ですので、本人と家族への説明が必要です。その他、ハロペリドールや抑肝散の有効例の報告があります。
- うつ症状
- 少量のSSRIやSNRIを試みてみます。うつ症状がアルツハイマー型認知症の前期症状あるいは初発症状になることもあるし、認知症の経過中に抑うつ状態を来たすこともあります。この場合抗認知症薬とSSRI、SNRIとの併用を考えます。
- 睡眠障害
- 非ベンゾジアゼピン系睡眠薬のうち超短時間型のゾピクロン、ゾルビデムを使用します。昼夜逆転には四環系抗うつ薬(ミアンセリン)と非ベンゾジアゼピン系睡眠薬の使用が有効です。
- 非薬物療法
- バリデーション(是認)療法は、患者の混乱した言動にも理由があり、その意味を認め受容と共感を目標とする療法ですが、その効果を評価することはまだ困難です。リアリティオリエンテーションは患者の現実の見当識を強化することにより行動や感情の障害を改善することが目的です。薬物療法と併用することにより効果が期待されています。
音楽療法や運動療法の評価は一定していません。認知刺激療法は脳に刺激を与え認知機能そのものの改善をはかろうとするもので、抗認知症薬との併用により認知機能への効果がみられています。
【成年後見制度の助言】
認知機能障害での成年後見制度により、医療や財政に関する意志決定の代行制度など、本人の権利を守るための意義がありますので、これについて本人や家族へ助言することが必要です。
《文献》
1) 日本神経学会 : 認知症疾患治療ガイドライン2010 コンパクト版2012,2012年,医学書院
2) 中村 健二他 : 認知症ハンドブック,2013年 医学書院
3) 中村 重信 : 私たちは認知症とどう立ち向かっていけばよいのだろうか,2013年 南山堂
4) 畑 信也 : 抗認知症薬・向精神薬の使い方,2012年 中外医学社
(2014.2.5更新)