この『前立腺肥大症診療ガイドライン』は、患者と医師が前立腺肥大症の最も効果的な診断法と最も適切な治療法を選択するための指針を提供することを目的としたものです。
現時点での前立腺肥大症の標準的な診断・治療の流れは図1のようになります。
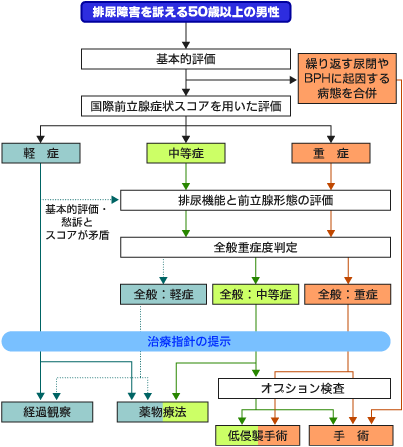
(図1)
【前立腺肥大症の診断法】
前立腺肥大症は、患者の日常生活の質〈QOL〉に影響を及ぼす疾患であり、このことから前立腺肥大症の病態は患者自身の症状の受け入れや不満の程度に大きく左右されます。大きな前立腺であっても排尿障害を認めない例もあり、客観的な検査は必ずしも症状とは相関しません。したがって,前立腺肥大症では症状の重症度を把握することが重要となります。
基本的評価
前立腺肥大症が疑われる50歳以上のすべての男性には、以下の初期評価をします。
- a. 初期評価項目
-
前立腺癌の検出率が高いPSA検査は,前立腺癌の除外診断のためにも初期評価として測定することが望ましい。* 病歴: 全般的な健康状態、併発疾患とその治療の詳細、既往症、排尿障害の原因となる他疾患、排尿状態の詳細な聴取 * 身体所見: 直腸指診や神経学的検査を含む * 尿検査: 試験紙法・尿沈渣 * 腎機能評価: 血清クレアチニン測定 - b. 緊急を有する症例の除外
- 尿閉を繰り返す症例と明らかに前立腺肥大症に起因する病態を合併する症例は、重篤な前立腺肥大症として区分し、手術などによる抜本的な治療が必要となります。
国際前立腺症状スコアを用いた症状の定量的評価
前立腺肥大症の症状の客観的な評価法として、国際前立腺症状スコア(I-PSS)とQOLスコアがあります。 自覚症状の評価に有用で、重症度診断の評価項目として、治療指針の決定や治療効果の評価に利用されています(図2)。
| まったく なし |
5回に1回 の割合未満 |
2回に1回 の割合未満 |
2回に1回 の割合 |
2回に1回 の割合以上 |
ほとんど 常に |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 最近1ヶ月間、排尿後に尿がまだ残っている感じがありましたか。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. 最近1ヶ月間、排尿後2時間以内にもう一度いかねばならないことがありましたか。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. 最近1ヶ月間、排尿途中に尿が途切れることがありましたか。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. 最近1ヶ月間、排尿を我慢するのがつらいことがありましたか。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. 最近1ヶ月間、尿の勢いが弱いことがありましたか。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. 最近1ヶ月間、排尿開始時にいきむ必要がありましたか。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. 最近1ヶ月間、床に就いてから朝起きるまでに普通何回排尿に起きましたか。 | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回以上 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1から7の点合計_____点
| 大変 満足 |
満足 | 大体 満足 |
満足・不満の どちらでもない |
不満 気味 |
不満 | 大変 不満 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の排尿の状態が、今後一生続くとしたらどう感じますか。 |
I-PSSは、排尿障害の症状に関する7項目の質問からなり、それぞれ0~5点の評価を行い、各項目点数を合計(総計35点)し,軽症(0~7点)、中等症(8~19点)、重症(20~35点)に分類します。同様に,QOLスコアは現在の排尿状態に対する患者自身の満足度を表す指標で、0点(大変満足)から6点(大変不満)までの7段階評価し、軽症(0~1点)、中等症(2~4点)、重症(5~6点)に区分します。
I-PSSで中等症もしくは重症と評価された場合、その状態を把握するために、さらに以下の検査が必要となります。
排尿機能と前立腺形態の評価
排尿機能の評価には尿流率測定と残尿測定が、また、前立腺形態の評価には超音波断層法による前立腺容積の測定が標準として用いられます。いずれも前立腺肥大症の客観的な評価に有用で、治療方針の決定や治療効果の評価に利用します。
- a. 排尿機能の評価
-
* 尿流率測定: 最大尿流率の測定は苦痛の伴わない検査で、尿が十分にたまった時点で専用尿器に排尿するだけの検査です。 * 残尿測定: 残尿測定は排尿効率の評価に用いられ、重症度判定と治療経過のモニタリングに用いられています。 従来、導尿で測定されてきた残尿測定は、最近ではその侵襲性から超音波断層診断法で非侵襲的に測定するのが望ましい。 * 排尿機能の重症度: 排尿機能の重症度は、軽症; 最大尿流率15ml/秒以上かつ残尿50ml未満、中等症; 最大尿流率5ml/秒以上かつ残尿100ml未満、重症; 最大尿流率5ml/秒未満または残尿100ml以上に区分します。 - b. 前立腺形態の評価
- 前立腺腫大の状態の客観的評価には、前立腺の容積測定と詳細な内部構造の観察に優れています。一般に広く用いられている経腹壁的超音波断層法でも、前立腺の容積測定と膀胱・前立腺の形態の観察は可能です。
*前立腺容積の重症度: 前立腺の形態上の重症度はその容積で表現し、軽症;20ml未満、中等症;50ml未満,重症;50ml以上に区分する。
前立腺肥大症の領域別重症度と全般重症度
症状(I-PSS・QOLスコア)、排尿機能(最大尿流率と残尿量)および形態〈前立腺容積〉を総合して判定します。
| 重症度 | 1. 症状 | 2. QOL | 3. 機能 | 4. 形態 | |
|---|---|---|---|---|---|
| I-PSS | QOL index | Qmax | RU | PV | |
| 軽 症 | 0~7 | 0, 1 | ≧15ml/s かつ <50ml | <20ml | |
| 中等症 | 8~19 | 2, 3, 4 | ≧5ml/s かつ <100ml | <50ml | |
| 重 症 | 20~35 | 5, 6 | <5ml/s または ≧100ml | ≧50ml | |
| 全 般 重症度 | 重症度判定項目数 | ||
|---|---|---|---|
| 軽 症 | 中等症 | 重 症 | |
| 軽 症 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | |
| 中等度 | 不問 | ≧2 | 0 |
| 不問 | 不問 | 1 | |
| 重 症 | 不問 | 不問 | ≧2 |
手術適応の決定のために必要と考えられる検査
- a. 内圧・尿流検査
- 治療効果を予測するのに有用。
- b. 膀胱尿道鏡検査
- 膀胱・前立腺部尿道などの観察に優れ、外科治療の場合、治療法選択の決定に用いられます。
【前立腺肥大症の治療指針の提示】
尿閉や明らかな前立腺肥大症関連合併症などが認められる患者では、外科治療が最も適切な治療法であります。前立腺肥大症は患者のQOLに影響を与える疾患であることから、上記以外の前立腺肥大症患者では治療法の選択にあたっては、患者と相談の上で治療法を決定すべきであります。
【前立腺肥大症の治療】
無治療経過観察
日常生活指導のみで、排尿状態が改善する症例が約1/4に認められることから、軽症患者では無治療経過観察も標準的な治療選択肢となります。症状悪化や合併症がみられるときは速やかに適切な治療を選択します。
薬物療法
全般重症度が軽症から中等症の患者が適応となります。
- α遮断薬
比較的効果の発現が早く、中長期の効果も認められており、薬物療法の標準的治療です。副作用として、起立性低血圧、めまいなどがみられますが、前立腺により選択性の高いものではその頻度が低いことが報告されています。 - 抗男性ホルモン薬
効果発現は緩徐で、中断により前立腺の容積は再度増大することが報告されています。副作用は性欲減退,勃起障害など、主に性機能に関連するものです。 - その他の薬剤
植物エキス製剤、アミノ酸製剤、漢方薬などがありますが、その作用機序や有用性についてはまだ十分解明されていません。
低侵襲治療
前立腺肥大症治療に対する先端医療として、レーザー、ステント、高温度療法などがあります。これらの治療法は、現時点では低侵襲性と安全性に関する報告はありますが、他療法と比較した有効性ならびに長期成績に関するデータは少なく、標準的な治療法となりうるか否か今後の検討が必要です。
手 術
尿閉や前立腺肥大症に起因する合併症のある患者と、総合評価で中等症から重症の患者が対象となります。手術は最も侵襲的な治療法ですが、手術により肥大した腺腫が切除されることで、排尿障害の改善には最も有効性があります。
TURPはより低侵襲で、確立した標準的な治療として広く普及しています。
尿道留置カテーテル
急性尿閉の緊急的処置として、また重篤な他疾患を併発している症例には、有用な治療法の一つです。しかし長期にわたる尿道カテーテルの留置は、患者のQOLを著しく低下させ、さらに尿路感染症や勝胱結石を合併する頻度が高くなります。間歇的導尿は患者自身や介護者が施行でき,QOLの保持の点で優れています。