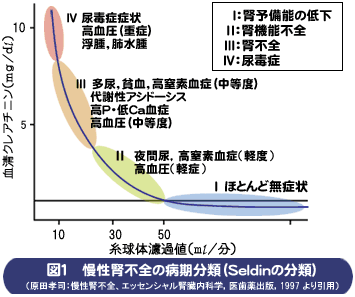
腎機能障害は重症度によって4つの時期に分かれます。(図1)
第1期は腎臓の予備能力が低下している時期で、ほとんど症状はありません。 第2期は腎機能が障害されている時期で、軽度ながら高窒素血症が認められます。
第3期からがいわゆる腎不全の時期で、貧血・中等度の高窒素血症・代謝性アシドーシス・高リン低カルシウム血症などの血液データの異常(図2)、多尿・高血圧などの症状が現れます。
第4期は浮腫・肺水腫・尿毒症症状を呈し、透析療法が必要となります。

腎不全の治療は、大きく (1)保存療法、(2)透析療法、(3)腎移植、の3つに分かれます。
(1)保存療法
障害の程度によって制限の度合いは異なりますが、a.運動の制限、b.食事療法(蛋白質・食塩・カリウム・リンの多い食事の制限、さらに糖尿病腎症ではカロリーの制限、乏尿=尿が作られない状態では水分の制限)、c.薬物療法(高リン血症改善薬:リン吸着剤、高窒素血症改善薬:経口吸着炭素剤、高カリウム血症改善薬:イオン交換樹脂、腎性貧血改善薬:エリスロポエチン製剤、アシドーシス改善薬:重曹、腎不全用アミノ酸製剤、骨活性化薬:ビタミンD3、など)、が基本となります。
(2)透析療法
透析療法の適応は、年齢や社会的環境によって若干異なりますが、血清クレアチニン値が8mg/dl以上、腎臓の機能が10%未満になったときが目安になります。 透析療法には、血液透析(HD)と腹膜透析(CAPD)の2通りの方法があります。日本では血液透析が主流で、腹膜透析の普及率は5%未満と低いのが現状です。血液透析では体外で透析膜を介して血液中の尿素窒素などを除去するため、血液の取り出し口(ブラッドアクセス)が必要となります。通常は恒久的な使用を目的に、動脈血を静脈に還流させる動静脈瘻(内シャント)を作製します。 内シャントの造設部位としては橈骨動脈と橈側皮静脈の間の吻合が一般的で(図3)、内シャントは継続して穿刺することで損傷し、閉塞することがあるので、できるだけ末梢の動静脈から造設することが原則です。
腹膜透析の原理は、専用のカテーテルを腹腔内(先端をダグラス窩近傍に留置)に挿入し、カテーテルから専用の透析液を腹腔内に注入、腹膜を透析膜として血管内の血液と透析液間で透析を行い、一定時間留置した腹腔内の透析液を体外に排出して尿毒物質や過剰な体液、電解質異常、代謝性アシドーシスを調整する方法です(図4)。
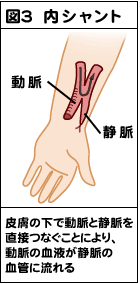
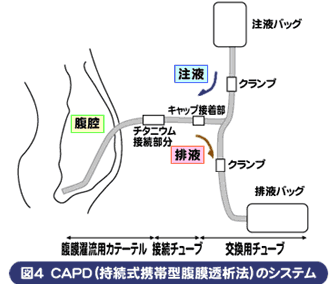
(3)腎移植
近年、腎移植はきわめて安全な治療法として確立されており、1年生着率も生体腎移植では95%以上になってきています。 現状では一部の疾患を除き、血液透析を必要とする患者のほとんどが腎移植の対象となり得ます。 その中で、腎移植の適応として、
- 年齢
65歳以上の高齢者の移植成績は他の年齢層に比べ有意に悪く、年齢そのもので適応を考慮するべきではないものの、実施にあたっては留意する点となります。
- 全身状態
全身麻酔、手術、免疫抑制剤の投与により術後全身状態が悪化する可能性があれば、移植は回避すべきであります。 また、悪性腫瘍を有する場合にも適応にはなりません。 悪性腫瘍が治療されている場合には、完治したとみなされる期間を過ぎたときのみ適応となります。 全身の感染症も移植の禁忌です。 透析患者には結核の合併も多く、完治してから1年間以上は経過を観察するべきです。
- ドナー(提供者)の適応
わが国においては献腎移植(死体腎移植)の数がきわめて少なく、生体腎ドナーの比率が高いことが特徴です。 生体ドナーを選択する場合、まず自発的意思ということが大前提ですが、いままで2親等以内の血縁者からの提供だけが許容されてきました。 しかし、最近では免疫抑制剤の進歩やドナー不足などにより、欧米では非血縁者からの提供も広く行われるようになってきましたが、現在のわが国においては夫婦間などのいわゆる家族内での提供のみが許容されています。