糖尿病を実地に診療する医師や生活指導に当たる
コメディカルスタッフのための「糖尿病治療ガイド2006-2007」
治療の前提である糖尿病の正しい理解のために、そして糖尿病を実地診療する医師や食事や運動などの生活指導に当たるコメディカルスタッフを対象にその指針として治療ガイドが策定されました。
近年、食生活の欧米化や生活様式の変化で糖尿病患者は著しく増加しています。2002年の推計ではその数は600万人を超すとされますが、一方、治療に当たる糖尿病専門医は4000人以下であり、糖尿病患者さんの大半は糖尿病の非専門医の診察を受けているのが現実です。したがって、そのような糖尿病非専門医とコメディカルスタッフのための指針が必要であり、専門医にとっても診療内容の標準化が必要なためにこの糖尿病治療ガイドが編まれました。
日本糖尿病学会が選任した委員からなる委員会により編集されたものですが、「糖尿病治療ガイド2006-2007」はその最新版です。1999年の初版の後、糖尿病学の進歩とエビデンス(臨床的証拠)に裏打ちされた新しい知見を踏まえて数回改定され、この最新版には、現時点での最先端の研究成果が盛り込まれています。
しかし、医学的知識が一般の人々にも広まりつつある現在では意識の高い糖尿病患者さんなら指導の下にこのガイドの理解は全く不可能というわけでなく、自分の受けている治療の理解と自身の動機づけ(自己管理の改善)にも役立つと思われます。
代謝全般の傷害された糖尿病では自己の膵臓から分泌されるインスリンの作用が不足しており、その結果、特徴的に血糖が高くなっています。とはいっても、糖尿病は単一な病ではありません。その分類は糖尿病の原因や疾患の状態がいくつかあるため単純なものではなく、病因と病態との組み合わせによりそのカテゴリー(種類)が増えます。
「糖尿病治療ガイド2006-2007」では実地診療の観点から糖尿病についての概念、分類、診断、治療、そして合併症についての系統的な理解が図られています。
1 成因分類、病態分類と糖尿病についての考え方
当ガイドの糖尿病 疾患の考え方の項では糖尿病の概念、病気の状態把握のための指標そして糖尿病の分類法が述べられ、インスリンが膵臓から分泌されない(分泌不全)、あるいはインスリンが効きにくい(インスリン抵抗性)ことに由来するインスリン作用の不足した疾患としての糖尿病が説明されています。
2 1型糖尿病、2型糖尿病とは
糖尿病の分類には成因に基づく病型分類(表1)と病態に基づく(病期)分類とがあります。成因に基づいては、1型糖尿病、2型糖尿病、その他の特定の機序、疾患による糖尿病、そして妊娠糖尿病の4群に分類されています。
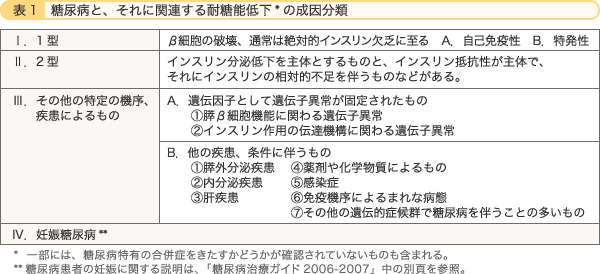
1型糖尿病は膵β細胞の破壊によるもので、通常は絶対的インスリン欠乏に至るとされ、さらに原因として膵β細胞が自己免疫性に破壊されるものと特発性(原因不明)のものとに分類されています。2型糖尿病では、インスリン分泌が低下するものとインスリン抵抗性を示すものとがあります。
病態に基づいての病期分類では、インスリン非依存状態とインスリン依存状態とが区別されます。この場合、インスリン依存状態とはインスリンが生命の維持に不可欠なケースを意味し、単に高血糖の是正にインスリンが必要なだけではインスリン依存状態ではないことに注意が必要です。
糖尿病のより深い理解のためには、このような糖尿病の成因による分類と病態による分類の双方の視点で考えることが重要で、これにより精細な分析が可能になります。たとえば1型糖尿病でインスリン非依存状態、2型糖尿病でインスリン不要な状態などです(図1)。
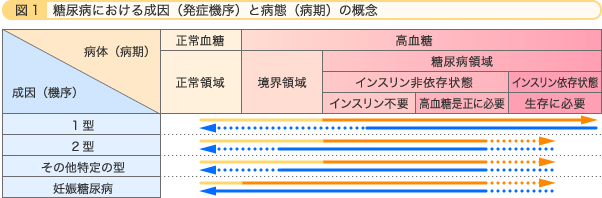
3 診断
最初、自覚症状や健診時の異常から糖尿病を疑うことになります。自覚症状としては口渇、多飲、多尿、体重減少などが、健診時の異常としては尿糖陽性、高血糖があります。診察室で問診と病歴聴取を行い、身体所見をとる作業を経て、空腹時や随時の血糖、HbA1cの測定が行われます。さらに詳細な情報を得るためにブドウ糖負荷試験が行われることもあります。(当ガイド、診断の項)
4 型の区分
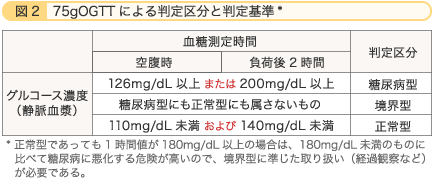
血糖検査の結果から、「正常型」、「境界型」、「糖尿病型」のいずれかの型に判定されます(図2)。
空腹時血糖で110mg/dl以下で75gブドウ糖負荷試験時の2時間値が140mg/dl以下の場合は「正常型」と判定されます。
空腹時血糖で126mg/dl以上、75gブドウ糖負荷試験時の2時間値が200mg/dl以上、あるいは随時の血糖値が200mg/dl以上のいずれかがあてはまれば「糖尿病型」と判定されます。
しかし血糖検査で分かることはあくまで血糖のみの情報であって必ずしも「糖尿病型」イーコール糖尿病でないことに留意しなければなりません。
血糖検査で「糖尿病型」と判定され、その上に①ฺ自覚症状がある、②ฺHbA1cが6.5%以上である、③ฺ糖尿病性網膜症を有するのいずれかがある場合、過去に「糖尿病型」を示した検査データがある場合は、1回の検査で糖尿病と診断され、治療が開始されることになります。
「糖尿病型」と判定されても自覚症状を欠きHbA1cが6.5%以下であり、かつ糖尿病性網膜症を欠く場合は、血糖の再検査の運びになります。その際は初診時とは違えた方法で検査することが推奨されています。例えば、初回空腹時血糖で判断された場合はブドウ糖負荷試験で判定するなどです。この再検査で初回と同じく「糖尿病型」と判定されれば糖尿病と診断されます。
問題は空腹時血糖110~125mg/dl, ブドウ糖負荷試験時の2時間値が140~200mg/dlの場合で、これは「境界型」と判定されます。このカテゴリーでは将来糖尿病を発症するリスクや心血管疾患のリスクが高いとされ、グレーゾーンを意味するので、発症予防の観点からの注意が重要です。
5 治療と血糖コントロールの指標
糖尿病は生活習慣病の代表的なもので患者さん自身の自己管理が大変重要です。自己管理の動機づけをし、コンプライアンスを高めるために患者さんの糖尿病教育が重要です。患者さんの心理的問題にも対処しなければなりません。
治療は食事療法、運動療法、薬物療法からなります。当ガイド、治療の項ではそれぞれの治療法が項を変えて解説されています。その究極の目的は「健康な人と変わらない日常生活の質の維持と健康な人と変わらない寿命の確保」です。血糖のコントロールのみならず代謝全般の改善により糖尿病合併症の発症と進展を防止しなければなりません。
この項では血糖値やHbA1c値、血圧、血清脂質について、コントロールの指標(目標値)と評価が述べられています(図3)。さらにフローチャートを用いた治療方針の立て方について解説されています。大きくはインスリン依存状態とインスリン非依存状態の二つの流れで考えることになります。

6 食事療法
食事療法は糖尿病治療の基本であり、すべての糖尿病患者に重要な治療です。しかし当ガイド、食事療法の項では実地医家にとって必要最小限な食事療法の知識が述べられているにとどまっているので、「食品交換表」や「「食品交換表」を用いる糖尿病食事療法の手引き」などを援用して具体的な食事指導に当たるのが望ましい。「食品交換表」は日本糖尿病学会と日本糖尿病協会が協力して執筆編集しているものですが、写真を多く用いるなど理解しやすい内容となっています。患者自身も食品交換表を活用することが望まれます。
7 運動療法
当ガイド、運動療法の項の運動療法は実地医家にとって必要最小限なものであるので「糖尿病療養指導の手びき」などを援用して具体的な運動指導を心がけることが望ましい。食事療法と並んで糖尿病治療の第一段階であり、すべての糖尿病患者に重要な治療です。しかし状態によっては運動により逆に糖尿病が悪化することもあり、運動療法を禁止あるいは制限したほうがよい場合があることを知っておく必要があります。
8 薬物療法
糖尿病の薬物療法は経口薬療法とインスリン療法に大別されます。
経口薬はその薬理作用から大きく3つに分類されます。Ⅰฺインスリン分泌を促進するものとして①ฺSU剤、②ฺ即効型インスリン分泌促進薬 Ⅱฺインスリン抵抗性を改善するものとして③ฺビグアナド薬、④ฺチアゾリジン薬 そしてⅢฺ腸管における糖の吸収を遅らせるものとして⑤ฺα―グリコシダーゼ阻害薬と細かくは5種類があります。
当ガイドの薬物療法の項ではインスリン療法の適応とインスリン製剤の種類についての説明があり症例を示しながらインスリン療法の実際的なやり方が説明されています。
インスリン療法はその作用不足を外因性インスリンの注射で補うものですが、できうるかぎり生理的なインスリン分泌動態をシミュレートすることにより生理的な血糖動態を再現することが望まれます。
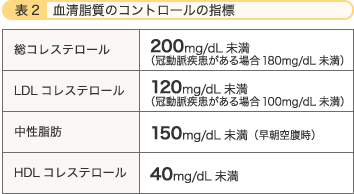
使用するインスリン製剤の特性を熟知した上で、インスリン依存度を把握し、製剤の選択、注射の回数と時間など具体的なインスリン治療法を決定することが必要です。また病態の変化によりインスリンの必要量は変化するので、その投与量に注意する必要があります。
糖尿病治療では単に血糖をコントロールするだけでなく代謝全般を改善する視点が重要で、血圧や脂質に関しても注意を払い、これらのコントロールに努めなくてはなりません(表2)。
9 急性合併症
患者さんの生命に直接かかわりうる重大なものとして急性糖尿病合併症があります。低血糖や昏睡などですが、適切な処置を施さないと生命が危機にさらされます。
10 低血糖
低血糖は薬物療法を受けている患者、とくにインスリン分泌を促進する作用のあるSU財と即効型インスリン分泌促進薬、あるいはインスリン療法を受けている患者に起こりうる副作用です。放置されれば昏睡に陥るのですばやく対処しなければなりません。ここでも低血糖に対する患者さんの教育が重要です。
11 いわゆるシックデイ
発熱、下痢、嘔吐などのストレスにより代謝が変調を来たし、血糖コントロールが乱れることがあります。ストレスの影響が治療効果を上回るこのシックデイの際には糖尿病ケトアシドーシスや高血糖高浸透圧昏睡などの急性合併症を起こしやすく、重症な場合には意識障害を引き起こすことがあります。この急性合併症への対応も重要であり、とくに初期治療における十分な水分補給(輸液)とインスリンを経静脈的に投与しインスリン作用を強化する必要があります。糖尿病専門医の受診までにおこなっておくべきでものです。シックデイではインスリンの注射量を変更する必要があるなど患者さんの教育も重要です。
12 慢性合併症(三大合併症、大血管障害、足病変)
罹病期間が長くなると眼、腎臓、神経に糖尿病の慢性合併症が出現してきます。最小血管障害(マイクロアンギオパシー)による網膜症、腎症、神経障害のいわゆる三大合併症がそれです。それ以外に大血管にも合併症を来たします。冠動脈硬化症や脳血管障害です。そして神経障害と血管障害が組み合わさって足の病変が生じます(糖尿病性壊疽)。
慢性合併症は、多くは初期では臨床症状がなく、検査でしかとらえられません。そのために必要な検査を定期的におこなっていく必要があり、実地医家としては、合併症の兆候を見落とさないことが重要です。また眼科との連携は重要であり、初診時には必ず眼科を受診させる。また合併症がすでにある場合には平行して専門医を受診させることも必要です。
おわりに
糖尿病治療ガイドを指針として糖尿病治療が行われますが、医師やコメディカルスタッフにとってその内容は部分によっては必要最小限なこともあり、十分なものではありません。先に述べた「食品交換表」以外に「糖尿病療養指導の手びき 改定第3版」、「患者さんとその家族のための糖尿病治療の手びき」、「小児-思春期糖尿病管理の手びき 改定第2版」など他の参考書も活用することにより、患者さんの指導は具体的なものとなります。また、これらの参考書は患者さんにとっても有用なものとなるでしょう。