1 はじめに

一口に癌といっても、全ての癌、全ての癌患者、癌の全経過に痛みが伴う訳ではありません。癌性疼痛の「成り立ち」は一つでないからです。また、疼痛治療の中にはある程度の侵襲を伴ったり、機能障害を余儀なくされたり、副作用を伴ったりするものも少なからず有ります。しかし、これらを引き換えにしても痛みを取ることを優先したい、と言う場面は日常的に頻繁にあります。そのくらい癌性疼痛は耐えがたいものなのです。それゆえ、それぞれの癌患者の病状に合わせた癌性疼痛治療が必要となり、画一的なものは有りません。
2 癌性疼痛の成り立ち
癌そのものが痛みを発するということは有りません。癌細胞がどんどん増殖するために組織・臓器の内圧上昇、圧迫、近隣組織・臓器に圧迫と浸潤などの影響を及ぼし、痛みを発します。また、癌は転移するため、転移した先の組織・臓器で同じことが起こり、さらに転移した先が神経や骨組織であると、それだけで痛みの原因となります。疼痛での原因は一つではなく、複合しているのが通例で、それらが病状の経過とともに複雑に変化していきます。それとともに患者の体力も衰弱し、治療の選択肢が変化してきます。ここに治療の難しさがあります。>>表1にはそれらの成因と対処方の一般的な概略を示します。通常、これらの中から単独、あるいは組み合わせて治療します。- 制癌治療
- 癌の基礎治療を行い、これを治癒させ、あるいは縮小させることが、すなわち疼痛を消失させ、あるいは軽減させるための最も重要な原因治療となることは言うまでもありません。そのために、外科手術、放射線治療、化学(抗癌薬)療法は不可欠です。これらの治療により疼痛コントロールが困難なときに、癌性疼痛治療が合わせて行われます。
3 癌性疼痛の対処法
癌性疼痛の治療法には薬物療法、神経ブロック、手術などの方法があります。その他にも理学療法(皮膚刺激法、運動療法、逆刺激療法、経皮的電気刺激療法、鍼療法など)や精神・心理・社会的療法(心理社会的介入法、リラクゼーション法とイメージ法、意識拡散法と再構成法、患者の教育、心埋療法と構造的支持、催眠術、精神面のカウンセリング、同病者支援グループなど)がありますが、ここでは紹介するのみに留めます。癌性疼痛治療について、それぞれの病状に応じて、>>表2のような基本的な考え、あるいは方針が考えられます。末期に近づくにつれて、侵襲の強い治療は適応しなくなります。また、以下に述べたように、癌性疼痛治療法には、画一的な、あるいは定型的なものはなく、様々です。このことは癌性疼痛治療が非常に困難で、多岐にわたることを示しています。
4 鎮痛薬の作用点と副作用
- 非ステロイド性消炎鎮痛薬 《グレードA》
- その源をアスピリンに持つ一連の薬剤で、解熱鎮痛薬とも呼ばれました。プロスタグランジンを合成する酵素、COX-1とCOX-2を阻害することにより、炎症を抑え、また侵害受容器の感受性を下げ、さらに脊髄においてCOX-2が痛みを増強するのを抑えることにより鎮痛作用を現します。アスピリンやジクロフェナック(ボルタレン®)は有名です。主な副作用は胃腸障害と血液凝固機能障害です。最近では、COX-2のみを阻害するものが開発され、副作用低下に役立っています。
- オピオイド 《グレードA》
- オピオイドにはμ作動薬、δ作動薬、κ作動薬の3種類があり、日常的にはμ(モルヒネ、ブプレノルフィン、フェンタニル、オキシコドンなど)とκ(エプタゾシン)が使用されます(ペンタゾシンはμとκの両作用を併せ持つ)。μ作動薬には副作用が多く、吐き気、便秘、痒み、呼吸抑制、多幸感、排尿障害(特に硬膜外投与時)、習慣性(いわゆる中毒)などがあります。一方、κ作動薬には目立った副作用はありません。
- 抗鬱薬 《グレードB、ときにA》
- 脳内のセロトニンやノルアドレナリン(これらをまとめてモノアミン)の作用を増強することにより抗鬱作用を現します。モノアミンオキシダーゼ阻害薬(MAOI)、最近では特異的セロトニン再吸収阻害薬(SSRI)や特異的セロトニン・ノルアドレナリン再吸収阻害薬(SNRI)が用いられます。副作用には眠気、ふらつき、眼圧上昇などがあります。
- その他 《グレードC1》
- 静脈内麻酔薬(ケタミン)、カルシトニン、抗痙攣薬(カルマバゼピン、フェニトイン、バクロフェンなど)、副腎皮質ステロイド(プレドニゾロンなど)、鎮静薬(ジアゼパムなど)なども癌性疼痛に効果がある場合も報告されています。
5 薬物療法
治療法には色々な方法があり、それぞれの痛みの部位、進行状況、一般状態、目標、などに合わせて、単独あるいは組み合わせて選択します。癌性疼痛治療全般に共通することですが、鎮痛作用に切れ目がないように(by the clock)服用する必要があります(図1)。ときに、痛みが特に増強することもあるので、ある鎮痛法をベースにして、その時々に鎮痛薬の追加(内服、注射)で対処することがある。これをレスキュー投与といい、オキシコドンなどがよく用いられます。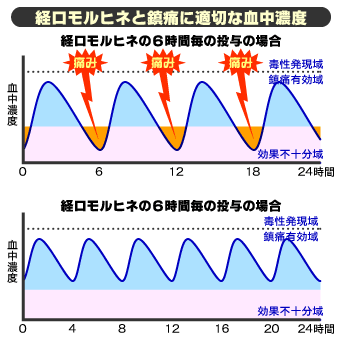
(図1)
モルヒネの投与時間と血中濃度
血中濃度を、鎮痛に必要な最低濃度と毒性が発現する濃度との間に保つ。そのために、時間を決めて規則正しく投与することが重要。(By the clock)。
- 経口投与 《グレードA》
- 経口薬の内服は最も簡単で侵襲を伴わない方法で、現在最も広く行われており、完全な終末期を除いて可能な方法です。非オピオイドとしては非ステロイド性消炎鎮痛薬、抗鬱薬、SSRI、SNRI、ケタミン、などが、オピオイド(モルヒネ受容体に働く薬剤)としてはコデイン、ペンタゾシン、モルヒネ、オキシコドンなどが用いられます。
夜間や外出時などの服用の煩わしさを回避するため、長時間(12時間や24時間)作用性の製剤(徐放錠)が開発されています。内服は、胃腸障害の副作用があり、調節性が劣ることや即効性に欠ける点も短所です。WHOは経口薬の使用法として「三段階ラダー」を推奨しています(図2)。これはオピオイド(特にモルヒネ)を主薬にし、補助薬を組み合わせ、病状の進行具合に合わせて鎮痛薬の量や種類、それらの組み合わせなどを3段階に調節(by the ladder)します。
痛みのある患者にオピオイドを投与しても、中毒は起こさないことが証明されています(詳しい説明は省略)。癌性疼痛治療にも当てはまりますので、中毒になるという懸念は不要です。
(図2)
癌性疼痛治療の三段階ラダー
モルヒネ(オピオイド)は段階目標にしたがって投与量を調節する。(第1目標)日中の痛みが軽減され、夜間よく眠れる、(第2目標)日中、安静にしていれば完全な徐痛が得られる、(第3目標)体重負荷時にも、体動時にも、痛みがない。そのために、比較的少量で投与を開始し、翌日その効果を判定し、痛みが残っていれば50%増量するという漸増法をとる。次第に増量していくと痛みが消失する量に達する。副作用、特に眠気があれば50%減量する。
- 経直腸投与(坐薬) 《グレードA》
- 坐薬も簡便な方法であるが、日本人には敬遠されがちです。大まかな特徴は、経口薬と類似していますが、胃腸障害がないのが最大の利点です。非ステロイド性消炎鎮痛薬、ペンタゾシン、モルヒネなどの製剤があります。
- 経皮投与(貼付薬) 《グレードA》
- 皮膚に貼り付けるだけで長時間(3日間)安定して作用します。現在、フェンタニルの製剤が使用されています。非常に手軽ですが、調節性乏しい、皮膚がかぶれるなどが欠点です。調節性を高めるために、レスキュー投与が必要となります。
- 経鼻投与 《グレードA》
- 鼻腔に噴霧する薬ですが、日本では未だ使用されていません。
- 持続皮下注射 《グレードA》
- 携帯型持続注入ポンプを用いて鎮痛薬を皮下に注入する方法です。専用のプラスチック皮下針もあり、注射の中では最も簡便で在宅管理も可能です。主にモルヒネ、フェンタニル、エプタゾシン、などのオピオイドが使用されます。
- 持続静脈内注射 《グレードA》
- 静脈内に持続注入ポンプを用いて鎮痛薬を注入する方法で、用いる器具や薬剤は持続皮下注射と共通です。通常は入院して行われ、長期化する場合は中心静脈カテーテルを挿入します。
- 硬膜外鎮痛法 《グレードA》
- 脊髄硬膜外腔にカテーテルを挿入し、鎮痛薬(主に水溶性の高いオピオイド)を持続注入する方法です。鎮痛薬が脊髄に直接作用し、運動機能を傷害せずに極めて強力な効果を現します。カテーテルが留置されるので、原則として入院が必要です。
μ作動薬を用いると、しばしば嘔気・嘔吐、排尿障害を伴います。κ作動薬のエプタゾシンは副作用が少なく、安定した効果があります。また、カルシトニンの硬膜外投与が著効したという報告をしばしば見ます。
局所麻酔薬を使用する場合は硬膜外ブロックといいます。 - 脊髄くも膜下、大槽内、脳室内投与 《グレードC1またはC2》
- 中枢神経系に直接投与する方法です。それなりのリスクを伴い、一般的ではありません。副腎皮質ステロイド薬、オピオイド、カルシトニン、抗痙攣薬、などが用いられます。
- 患者管理除痛法(PCA) 《グレードA》
- 投与される鎮痛薬の量を患者自身でコントロールする方法で、そのための装置が開発されています。これにより、夜間でも自由に鎮痛薬を使用できる、そのため患者に安心感が得られる、人手を煩わす気兼ねが不要となる、などの利点があります。一方、薬物の乱用、過量投与による副作用などが欠点となります。
- 埋込み式注入ポートと注入ポンプ 《グレードA》
- 治療が長期にわたるときは、注入ポートや注入ポンプを皮下に埋込むことが出来ます。これにより、行動範囲が広がり入浴なども可能となるため、自立して社会復帰や自宅療養も可能となります。
6 非薬物療法 侵襲的治療法
- 神経ブロック(薬剤による神経遮断) 《グレードA》
- 痛みを感じている神経を局所麻酔薬や神経破壊薬(最近はより安全な高周波熱凝固も用いられる)により、麻痺させる。これにより疼痛は取れるが、痺れた感覚も伴います。局所麻酔薬を用いれば一時的な鎮痛が得られるが、繰り返し行う必要があります。神経破壊を行えば、作用は長期(数ヶ月-3年)に及びます。一方、運動神経が含まれていると、運動麻痺、筋力低下、膀胱直腸障害などを伴うことがある。これらの障害を避けるためには脊髄後根のみを遮断するくも膜下ブロックが有効です。
カテーテルを留置して、持続的に薬剤を注入し続ける方法があります。持続硬膜外ブロックが代表的であるが、運動麻痺や筋力低下、低血圧などを伴います。持続カテーテルにより、まれに硬膜外感染や血腫を伴うことがあるのが欠点です。硬膜外腔に水溶性オピオイドを注入すると硬膜外鎮痛法となります(硬膜外投与法を参照)。 - 手術による神経遮断 《グレードB、ときにA》
 手術により痛みを感じている神経を切断する方法です。結果は神経ブロックと類似していますが、メスを加えるのが欠点です。色々な部位で神経が切断されますが、末梢から順に、末梢神経切断術、脊髄後根切断術、後根進入部破壊術、前側方コルドトミー(脊髄路切断術)、脊髄交連切開術、下垂体切除術、などがあります。
手術により痛みを感じている神経を切断する方法です。結果は神経ブロックと類似していますが、メスを加えるのが欠点です。色々な部位で神経が切断されますが、末梢から順に、末梢神経切断術、脊髄後根切断術、後根進入部破壊術、前側方コルドトミー(脊髄路切断術)、脊髄交連切開術、下垂体切除術、などがあります。
神経増強術は脳幹部を電気刺激することにより、内因性オピオイドの分泌を促して鎮痛を得る方法です。
経皮的コルドトミーは注射針を刺して高周波熱凝固により脊髄路を切断する方法で、下垂体ブロックは鼻腔より下垂体に針を刺して下垂体を破壊する方法です。いずれもメスを使うことなく低侵襲です。
これらの手術は限られた一部の施設で行われています。- 脊髄刺激療法 《グレードA、ときにB》
- 痛みを感じている脊髄分節に相当する硬膜外腔に電極を挿入して(硬膜外ブロックと全く同じ方法で簡単にはいる)、脊髄を電気刺激します。効果が好ければ刺激装置を皮下に埋込み、社会復帰も可能となります。手術による神経遮断と異なり、神経には一切触れないので、障害が少ない。まれに硬膜外感染や血腫を伴うことがあるのが欠点です。
7 おわりに
癌性疼痛治療は、このように様々な方法が考えられ、行われています。これは、完全な、決定的な治療がないことを示しています。絶えず変化する病状と痛みに対し、適切な治療法を選択し組合わせることが重要です。これには、患者とその家族、主治医の連携のみによって達成されます。